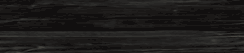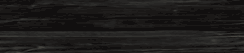茶道の歴史
HISTORY OF CHADO 茶道の歴史
HISTORY OF CHADO
1.茶の伝来
2.茶勝負(闘茶)のはじまり
3.闘茶の3要素(茶室・道具・作法)
4.書院茶の湯(室町時代)
5.そして侘び茶へ(茶の湯の確立)
6.千利休の登場
7.三千家(表千家・裏千家・武者小路千家)
8.江戸時代以降の茶の湯
 1.茶の伝来
1.茶の伝来
栄西禅師(えいさいぜんし,岡山市吉備津神社・神職の子供)が1100年代後半に中国からお茶の木を持ち帰り、京都の栂尾高山寺(とがのおこうざんじ)の明恵上人(みょうえしょうにん)におくり、植えたのが日本でのお茶の栽培の始まりといわれている。その後、他の地方でもお茶の栽培が行われたが、栂尾のお茶を本茶(ほんちゃ)、他の地方で栽培されるお茶を非茶(ひちゃ)と呼び、区別されていた。
2.茶勝負(闘茶)のはじまり
各地でお茶の栽培が盛んになると、各地方からのお茶を飲み比べて、本茶(栂尾茶)とそれ以外の茶(非茶)の味を当てる、いわゆる闘茶(とうちゃ)が行われた。これは現在でいう「賭博」のような性質をもって盛んにおこなわれ、高価な茶道具などが賭物として積まれた。こういった闘茶は、いろいろな形式と内容をもちながら鎌倉末期から南北朝時代に大いに盛んになった。
3.闘茶の3要素(茶室・道具・作法)
闘茶が盛んになるにつれて、闘茶を行う場所の確保が必要となった。これが後の茶室(ちゃしつ)の始まりである。
また、闘茶をするためにそれぞれの道具、たとえば茶碗(ちゃわん)・茶筅(ちゃせん)・茶器(ちゃき)などが必要であり、その道具も自分の自慢の道具を出すようになり、そういう面での競争もさかんとなった。これが茶道具(ちゃどうぐ)の始まりである。次に、闘茶を行うための順序・作法が次第に形作られ、これが茶の作法(さほう)の始まりとなった。
現在でも京都の建仁寺(けんにんじ)で行われている、四頭(よつがしら)の茶会に、その作法の名残がみられる。
4.書院茶の湯(室町時代)
鎌倉時代のころから、茶を通じて人が集まるようになった。、この茶寄合(ちゃよりあい)は、人間関係の形成など、単なる遊興の喫茶だけではなくなった。ここで初めて茶の湯が成立したといえる。
室町時代になって、書院造の建物が出現すると同時に、茶の湯は飛躍的な発展を遂げた。これを書院茶の湯と言う。これは、茶室の隣に設置された部屋で茶を点てて(たてて)茶室に運ぶ、点茶と喫茶が分離したものであった。
5.そして侘び茶へ(茶の湯の確立)
琵琶法師の息子である村田珠光(むらたじゅこう)は、禅僧である一休宗純(いっきゅうそうじゅん)に参禅し、茶禅一味(ちゃぜんいちみ)の境地を開いたとされている。つまり、茶道と禅道を根本的に同じ物と考え、禅の考えを大きく茶道に取り入れたものである。
この侘び茶(わびちゃ)の特徴は、美を否定し、質素で乏しい事を良しとしている。したがって、茶室は4畳半と狭く、茶庭や礼儀作法・道具など、すべてに至るまで「侘び」を追求した物に変わっていった。道具に莫大な財産を投入した書院茶の湯とは異なり、「持たない」事を茶道の美とした。
 6.千利休の登場
6.千利休の登場
千利休は、堺の商人の子として生まれた。18才の時、武野紹鴎(たけのじょうおう)に入門し、侘び茶を大成した。この二人の手により、茶道の工夫がさらに進んだのである。織田信長が室町幕府を倒して政権を樹立すると、信長は茶頭(ちゃとう)として利休を召して、茶の湯の権威を誇った。信長が本能寺の変によって倒された後も、豊臣秀吉に仕え、利休の茶の湯は一世を風靡することとなる。このころになると、茶の湯と言えば千利休の茶の湯を指すことになり、茶の湯での天下統一がはかられた。
7.三千家(表千家・裏千家・武者小路千家)
その後、宗旦(そうたん)の息子のうち三人がそれぞれの流派をたて、千家は三千家にわかれることとなる。これが、表千家(おもてせんけ)・裏千家(うらせんけ)・武者小路千家(むしゃこうじせんけ)の始まりである。
8.江戸時代以降の茶の湯
江戸時代になると、古田織部(ふるたおりべ)、小堀遠州(こぼりえんしゅう)、藪内剣仲(やぶのうちけんちゅう)らにより大名の茶が盛んになった。ちなみに、女性が茶の湯にかかわるようになったのは明治時代になってからである。
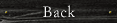
E-mail
: s-tnk@naigaijp.com
|